- シリコンバレーでは「996(週72時間労働)」が再び注目されている
- Cognition AI・Cursor・AnthropicなどのAIスタートアップが兆円単位の評価額を記録
- Rampの経費データが週末オフィス稼働の実態を裏付ける
- 日本の経営者の中には労働時間増で業績向上を狙う動きもある
- AIが生む富と過酷労働というコントラストが、世界の働き方に問いを突きつけている
そもそも996ってどういう意味?
「996(きゅうきゅうろく)」中国のテック業界で広まった労働スタイルを指す言葉のこと。午前9時から午後9時まで、週6日勤務=週72時間労働を意味します。アリババやバイトダンスといった巨大企業が成長する過程で定着した働き方で、一時は「成功のための必須条件」とまで称賛されました。
しかし同時に、過労死やメンタル不調など健康被害が社会問題化し、中国国内でも違法性が指摘されてきた経緯があります。本来は批判の対象である「996」ですが、AIゴールドラッシュの熱狂に包まれたシリコンバレーでは、成果を急ぐ企業や個人の間で再び脚光を浴びているのです。
シリコンバレーで996が復活する理由
「996」的な過酷労働が注目されている背景には、AIブームが生み出した強烈な経済的圧力があります。
代表的なのが、アメリカ・サンフランシスコに拠点を置くスタートアップ「Cognition AI」。同社が開発した自律型AIコーディングツール「Devin」は、2023年の創業からわずか2年で企業価値1.5兆円*1規模に到達しました。
短期間での上場や買収といった出口戦略を強く意識せざるを得ない状況となり、そこで働くエンジニアには「週72時間労働」を受け入れざるを得ない空気が生まれています。
CursorやAnthropicといった他のAI企業も同様に兆円単位の評価額を獲得しており、シリコンバレー全体が「短期間で結果を出すための過密労働」へと傾いているのです。
AIゴールドラッシュと出口戦略
AIスタートアップの世界では、「短期間で飛躍的成長 → 上場・買収」で利益を得る“出口戦略”が理想とされています。
たとえば、AIコーディング支援ツール Cursor(開発元:Anysphere) は、2025年6月に 9億ドルの資金調達を行い、企業評価額を99億ドル(約1.2兆円相当)*3に引き上げました。
また、AI界隈で最も注目される企業の一つ Anthropic は、2025年9月に シリーズFで130億ドルを調達し、評価額を1830億ドル(約23兆円規模)*4 に到達しています。
こうした大規模な評価額の跳ね上がりは、創業者や投資家に対して「このバブルを逃すな」「必ずリターンを出せ」というプレッシャーを与えます。その結果、従業員やエンジニアには「成果を出すまで働き続けよ」という文化が染み付き、996的な過酷さを自ら選ぶ風土が生まれてしまうのです。
Googleの「Code Red」と60時間労働
シリコンバレーにおける働き方の転換点となったのは、2022年11月に公開されたChatGPTです。その直後、Googleは自社の危機を示す「Code Red」を社内に発令しました*4。AI分野での優位性を脅かされると感じた同社は、経営陣から現場まで緊張感を高めることになったのです。
その象徴が、Google共同創業者の一人 Sergey Brinの現場復帰。BrinはAI開発チームに直接関与し、社内では「最低でも週60時間は働け」という趣旨の発言が報道されています。
こうしたトップレベルからの強いシグナルが、業界全体に「成果を出すには過密労働が不可欠だ」というメッセージを広げ、996の文化を正当化する追い風となりました。
Z世代にとっての“生存戦略”
996の再燃は、経営者や投資家の野心だけでなく、キャリアを始めたばかりのZ世代にも深く関わっています。
AIの進化は、リサーチや基礎的なコーディングといった初級エンジニアの仕事を急速に代替しつつあります。その結果、ジュニア層の求人は大幅に減少し、エントリーレベルのポジション獲得がますます難しくなっています。*5
こうした状況で、若手の多くは「996でも働けます」という姿勢を自らの売り込み手段にせざるを得ません。これは野心というより、業界で生き残るための“生存戦略”です。
つまりシリコンバレーでは、Z世代にとって過酷労働は選択ではなく必然になりつつあるのです。
データが裏付ける「シリコンバレーの土曜出勤」
996が単なるSNS上の話題ではなく、実際に広がっていることを示すデータがあります。
法人向け経費管理サービスを手がけるフィンテック企業 Ramp の経済ラボが、2025年1月から9月までの利用データを分析したところ、サンフランシスコのテクノロジー企業で土曜日の経費利用が急増していることが明らかになりました*6。
特にフードデリバリーや配車サービスの支出が際立っており、これは社員が週末にオフィスへ出勤し、深夜まで働いていることを示す動かぬ証拠となります。つまり「週72時間労働」は精神論ではなく、もはやデータとして可視化された現実なのです。
996は日本でも流行するのか?
日本で「996」的な働き方が広まる可能性は、法制度面では極めて低いと言えます。労働基準法第32条では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることは原則禁止と定められています。*7
月45時間、年360時間を超える残業は原則禁止とされており(特別条項を除いて)*8、週72時間という働き方は法の枠組みから明らかに逸脱します。
そのため、「996」という働き方が日本で普及することは現実的ではありません
「労働時間を伸ばしたい経営者」も多い
日本の中小企業経営者を対象にしたアンケート調査では、「1日の平均労働時間が10時間以上」という回答が約29%に上るという結果があります。*9
また、「もっと長い時間働きたいか?」という意識調査では全体の10.9%が「増やしたい/やや増やしたい」と回答しており、残業代を稼ぎたいという動機も背景にあります*10。
経営者の圧力と労働者側の期待が交錯すれば、制度のすき間で過重労働が蔓延するリスクもゼロではありません。
したがって、表向きには法制度がブレーキをかけてくれますが、実質的には“996的傾向”が局所で芽を出す可能性は残されている……というのが現実的な見立てです。
まとめ
シリコンバレーで再び広がる「996」は、単なる流行ではありません。
Cognition AIやCursor、AnthropicといったAIスタートアップが兆円単位の評価額を記録し*1 *2 3、GoogleはChatGPT登場後に“Code Red”を発令、Sergey Brin自ら「週60時間」労働を示唆しました。さらにRampの経費データが週末稼働の実態を裏付けています。
AIゴールドラッシュが生んだ莫大な富と、その裏側にある過酷な労働文化。これはシリコンバレーだけでなく、日本社会にも「働き方の未来」を問いかけています。
あなたは、どちらを選びますか——“成果のための996”か、それとも“持続可能な働き方”か。
本記事の情報ソース
- *1:「Cognition 公式X(旧:Twitter)」より
- *2:CURSOR「Series C and Scale」より
- *3:Anthropic 「Anthropic raises $13B Series F at $183B post-money valuation」より
- *4:NYT「A New Chat Bot Is a ‘Code Red’ for Google’s Search Business」より
- *5:WIRED 「AI Is Eliminating Jobs for Younger Workers」より
- *6:Ramp Economics Lab「Our data shows San Francisco tech workers are working Saturdays」より
- *7:厚生労働省:「労働条件・職場環境に関するルール」より
- *8:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 P2 P3」より
- *9:大同生命「経営者の1日の平均労働時間「10時間以上」が29%」より
- *10:厚生労働省「労働時間制度等に関するアンケート調査結果について(速報値)」より
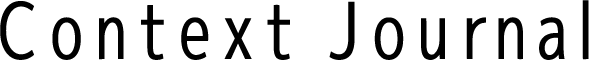
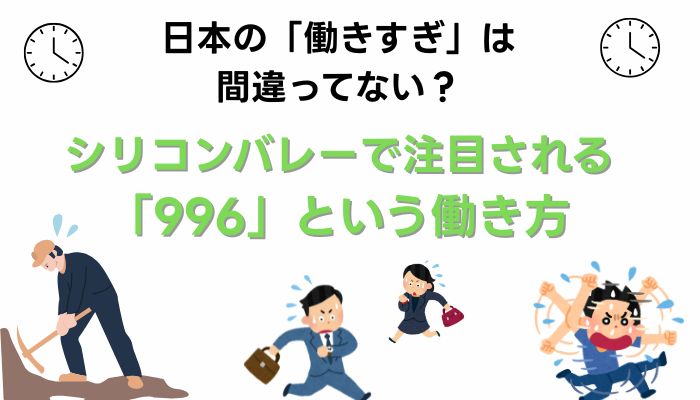

コメント